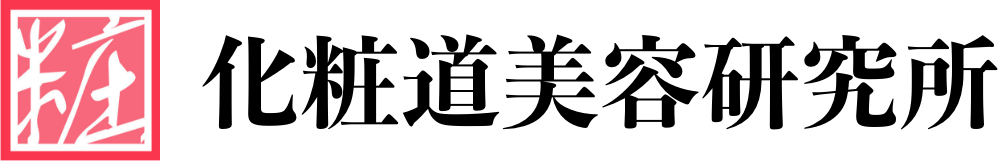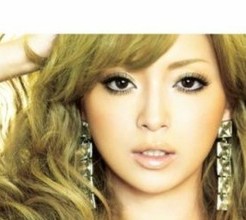メイクの起源 ―憑依・変身
フランス南部ドルドーニュ地方に人類最古の絵画「ラスコー壁画」がある。およそ2万年前のものだ。
文字が生まれるのはこの壁画から1万5先年後。エジプトのヒエログリフ、中国の象形文字、インドのインダス文字、メソポタミアの楔形文字、世界史定番の4大文明を彩る文字たちが発明され文明は「記録」できることになった。
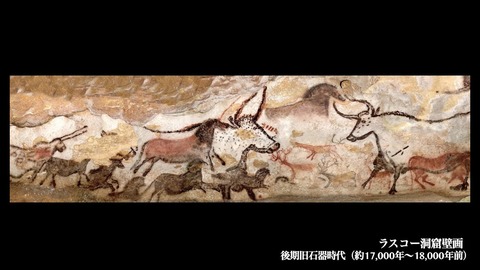
ラスコー壁画
記録をしたかったのか、誰かに見せたかったのか、はたまた単なる落書きか。当時の風俗を感じることができる貴重な遺産だが、文明を「記録」するには至っていない。落書きだとすればクオリティは高い
―――――――――――――――
文字は徴税官が税務記録を取ることから始まり、
その後、記録を取る・残す役割からエンターテイメントの世界に進出する。
シュメール人が書いた世界最古の文学「ギルガメシュ叙事詩」は英雄ギルガメシュ大王の冒険活劇、ホメロスの「イリアス」「オデュッセイア」はトロイア戦争の英雄たちの物語。
どちらも戦争の「記録」かもしれないが英雄物語として読者を楽しませにきているのは間違いない。これらを皮切りに物語文学、悲劇、喜劇がどんどん書かれ文字を読めるアッパー層に大ウケする。
これらを読んだ貴族たちがトロイア戦争の英雄アキレウスやヘクトールになりきりたくなったのだろう。戦地に行きたくないけど、みんなの前でカッコつけたい。そんな貴族のお遊びから生まれたエンタメが「演劇」。ギリシャでは演劇専門の劇場が複数発掘されていて古代ギリシャではすでに民衆の娯楽になっていたようだ。
そこそこの規模の舞台に立つ役者たちがばっちりとメイクしていたことは想像に難くない。
勇者なら勇者の装いを
戦士なら戦士の装いを
魔法使いなら魔法使いの装いを
僧侶なら僧侶の装いを
遊び人ならメイクは尚更必要だ。
役柄は人だけではないモンスターや悪魔だって登場する。メイクはもちろんのこと、被り物だって必要だ。メイクや衣装は観客に役柄を識別させるための必須手段。その役割は演技力と同等に大きい。
演者はメイクをすることで役柄に「変身」する。

劇団四季「ライオンキング」より
被り物と王族風衣装でライオンの王であることを端的に表しているライオンなのに役者の顔をあえて晒すというのがポイント
―――――――――――――――
舞台に立って大衆の注目を浴びるのは権力者にも通じる。特に古代世界では神の代理人たる神官が権力を持ち、民衆の前では神の使いを演じなければいけない。日本の天皇にいたっては神そのものだし、現代の政治家とは演じるレベルが違う。
クレオパトラは神と唯一対話できるファラオの後継者として権力を正当化した。民衆の前でファラオを演じるため、感染予防以上にメイクは重要な手段だったと思う。きっと一般民衆では手に入らないような希少な岩石(アイシャドウ)を使って神々しさや威厳を演出したはず。
ファラオになりきるためメイクをすることで神に「憑依」する。
お抱えメイクさんの心労たるや計り知れない。

生前もしくは死後すぐに描かれたとされる最も古いクレオパトラの肖像画
肖像画を見ると肌は白く、赤毛の天パ、装飾品はヘアバンドにイヤリングとネックレス、アイシャドウよりアイラインを強調しているのがわかる。後世の創作よりシンプルに感じるが当時ではこれがゴージャスだったのだろうか
―――――――――――――――
民衆の前に立って何かをする、注目を集めてショーを披露する。その起源は村のお祭りらしい。村の神官が村人の前で今年の豊作を祝い、来年の豊作を祈る。
祈祷が終われば酒宴が始まり、村人たちは太鼓を叩いたり、踊ったり、ときには寸劇を披露したりもしただろう。ちょっとした学芸会みたいなノリだ。
次回は村合同のお祭りにしよう。それならもっとたくさん人が集まる。せっかく人が集まるならステージも用意してメイクもして衣装も舞台装置も揃えて本格的にやろう。
舞台の規模が大きくなると必然的に観客との距離が遠くなり、演者が認識されずらくなる。そうなるとメイクも衣装もどんどん派手になる。メイクは役柄を認識させることはもちろん、遠くからでもクリアに映る「視認性」を高めるためのツールでもある。
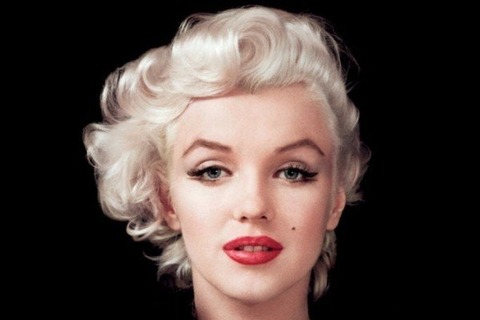
マリリンモンロー
1960年代アメリカのセックスシンボル
舞台女優として売れっ子になった彼女は一番遠くにいる人にもきちんと自分を認識できるように
どんどんメイクを濃く派手にしていった。
特徴的な彼女のメイクはファンサービスとして生まれたが奇しくも視認性の向上を求めた結果こうなった。
本人曰くセクシーなメイクと衣装はノーマジーンがマリリンモンローという役柄に入る儀式のようなもの、だそうだ。
(映画「マリリンモンロー」より)
―――――――――――――――

マイケルジャクソン
世界で一番CDアルバムを売ったスーパースター
当然ライブは数万人規模が動員されるためメイクにも高い視認性が要求される。
そんな彼がメイク道具で愛用したのが「マッキー」。言わずと知れた日本を代表する文房具。どんなことがあっても絶対にメイク崩れしないと絶対の信頼を置いていたそう。
―――――――――――――――
遠くから見てもはっきりと対象物を認識させる視認性の向上は日常生活にも欠かせない。交通標識や広告物などは遠くからでも認識できないとその意味をなさない。
文字を大きくすることはもちろん色の明度と彩度を上げ、寒色よりも暖色を使う。黄色、赤、オレンジが多様されるのは視認性を高くしたいが所以である。

黄色と紫でサイケデリックカラー
反対色を組み合わせることでより対象を目立たせることができる。
黒地に白、白地に黒は定石
―――――――――――――――
視認性の問題はメイクを考える上でとても重要なファクターということがわかる。
相手が遠ければ遠いほどメイクは濃くし、
逆に近ければ濃度もそれに合わせないといけない。
パーティーの距離感でマイケルジャクソンをやってはいけない。
メイクの濃い薄いは、見せたい相手との距離感で決まるといっていい。

映画「里見八犬伝」より
目周りのラインを極端に上げることでヒールであること、ヒダ衿(エリマキトカゲ)の衣装はその中でも階級が高いことを演出している

ドラマ「勇者ヨシヒコ」より
極端に大きいまつ毛、しかもそれを青く塗ることで意図的に視認性のズレを作り笑いに昇華している。視認性のコントロールを誤ると笑われるという好事例。メイクさんの腕と女優の演技が素晴らしい。

中世ヨーロッパの貴族ヘア
とにかく髪型は大きければ大きい方がいい。そんな狂った価値観が西欧で流行っていたそうだ。
パーティーの距離感で頭に船を乗せる。
視認性のコントロールを誤ると後世の人間に笑われるということがわかる。
―――――――――――――――
メイクの強弱は見てほしい相手との距離感で決まる。TPOに応じてメイクの強弱ををコントロールすることは、メイク手法の前提となる。
カテゴリなしの他の記事


-赤坂- 化粧道美容研究所
東京都港区元赤坂1-1-7
オリエント赤坂モートサイト506
年中無休/24時間営業・出張可